電気料金の削減法や消費電力削減のアイテムテクニックをご案内。
プロのコンサルタントが気になる法改正やニュース、アイテム情報も満載です。
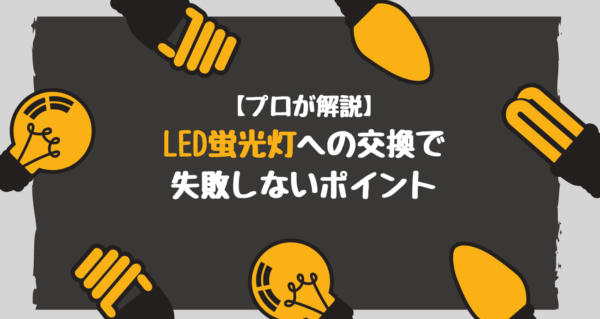
企業や施設の照明を蛍光灯からLEDに交換することは、エネルギー効率の向上、維持管理コストの削減、そして作業環境の質の改善を実現します。 LED蛍光灯の交換には工事不要タイプと、工事必要タイプの2種類があり、工事不要タイプ…

近年、企業経営において「ESG経営」が注目されています。 しかし、ESG経営がどのようなものなのか、概要や注目されている背景が分からない方も多いでしょう。 ESG経営とは、Environment(環境)、Social(社…

電気代高騰が続く中で、「水道光熱費を少しでも削減できる方法はないかな」と思っている方もいるのではないでしょうか。 省エネ効果を少しでも高めるために、エネルギーの見える化と、自動で省エネができるエネルギーマネジメントシステ…
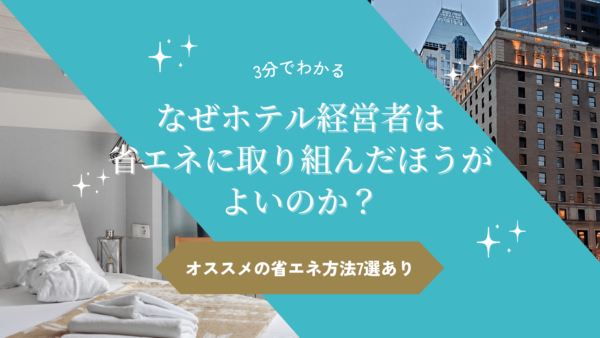
「水道光熱費が非常にかかる」 「これ以上の省エネ方法が思いつかない」 こんな悩みを持っているホテル経営者もいるのではないでしょうか。 ホテルの経営者に省エネへの取り組みが求められている理由は3つあります。 温室効果ガスを…
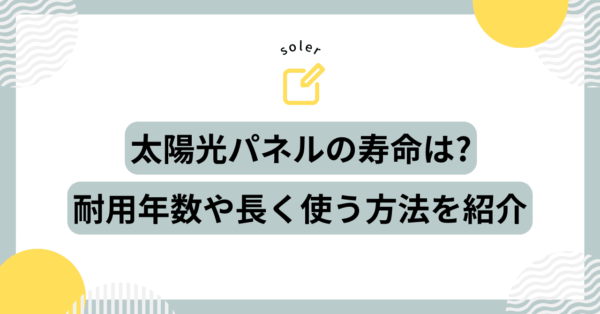
「太陽光パネルってどのぐらい持つんだろう?」 「業者によって言ってること違うし一般的な情報を知りたい」 こんなお悩みありませんか? 太陽光パネルの寿命は、約20-30年と言われています。 太陽光パネルの効果をあげ続けるに…
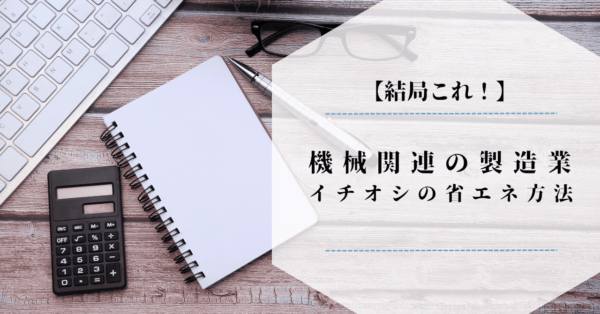
「省エネに取り組みたいけど、何から始めればよいかわからない」 「効果的な省エネ方法はあるのか?」 「なぜ省エネが推奨されているのか知りたい」 など、悩みのある方はいませんか? 機械関連の製造業は、工場の稼働している機械や…
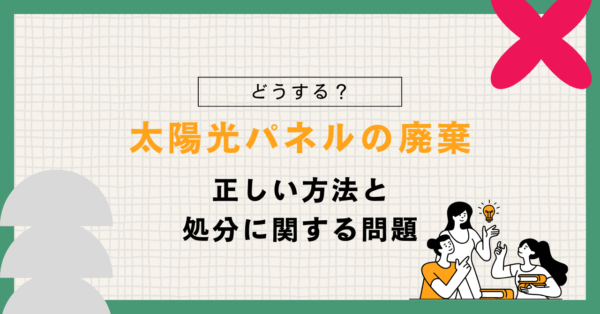
設置した太陽光パネル(ソーラーパネル)が不要になった際は、廃棄・処分を検討する必要があります。 しかし、太陽光パネルの廃棄については事前知識がないことも多く、結果として不適切な処分の仕方をしてしまうケースも少なくありませ…
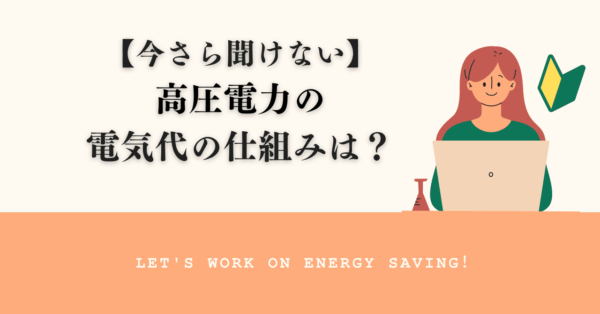
「高圧電力の電気代の仕組みがわからない」 「この項目はどういう意味?」 「まずは自社の電気代を把握したい」 省エネの最初の一歩は、まず自社の電気代からどこが削減できるのか把握することがポイントです。 ですが、家庭と比べて…
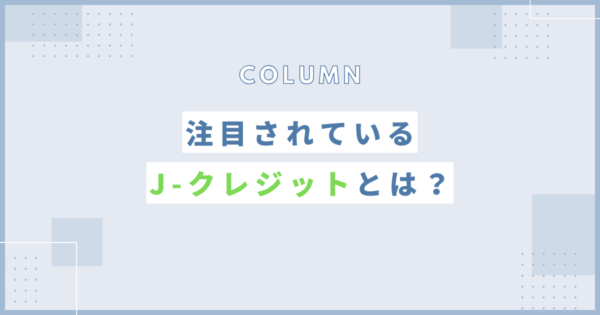
企業経営における指針の一つとして、国内でも環境に対する意識の高まりを感じる昨今、「J-クレジット制度」の利用を検討する企業も増えています。 しかし、その必要性や具体的な申請方法など、具体的なポイントを理解している人は多く…
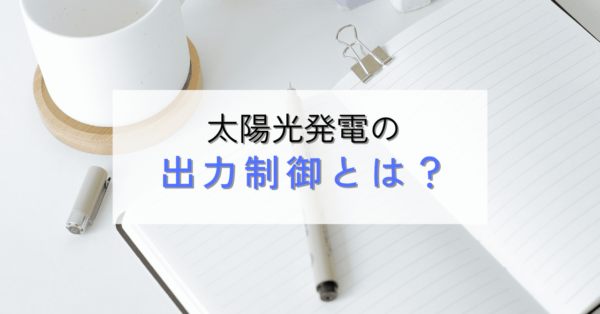
太陽光発電を取り入れる事業者が増える中、比例するように増加しているのが「出力制御」です。 出力制御とは、需要と供給のバランスを保つため、発電量をコントロールすることです。 太陽光発電を行う事業者にとって、出力制御は非常に…