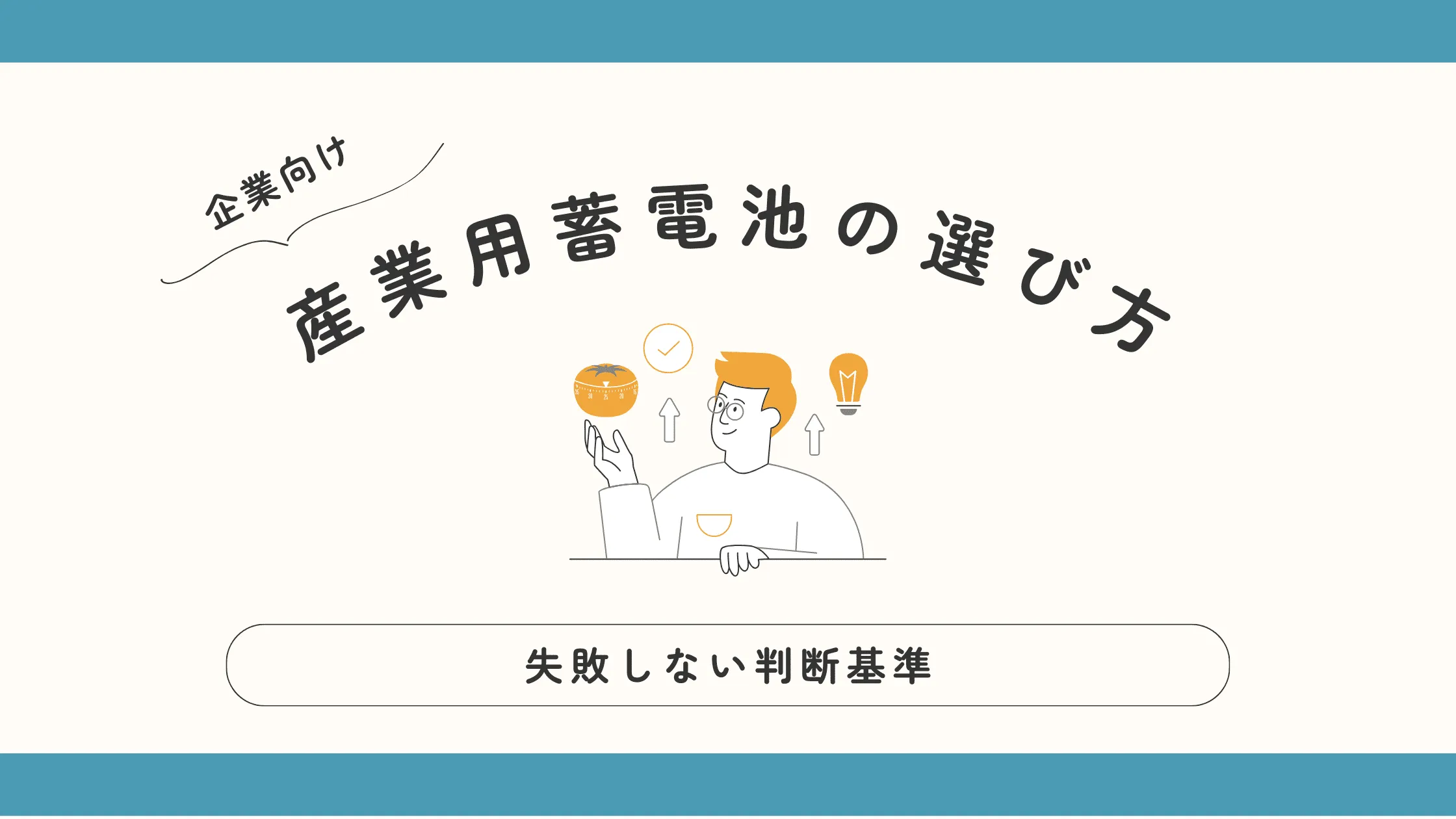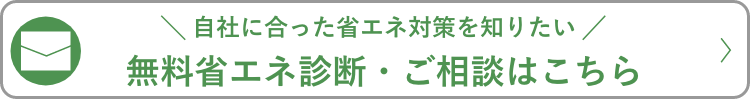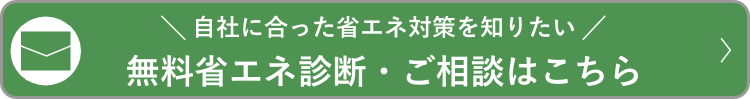投稿日:
企業が取り組むべきエネルギー管理と省エネ戦略
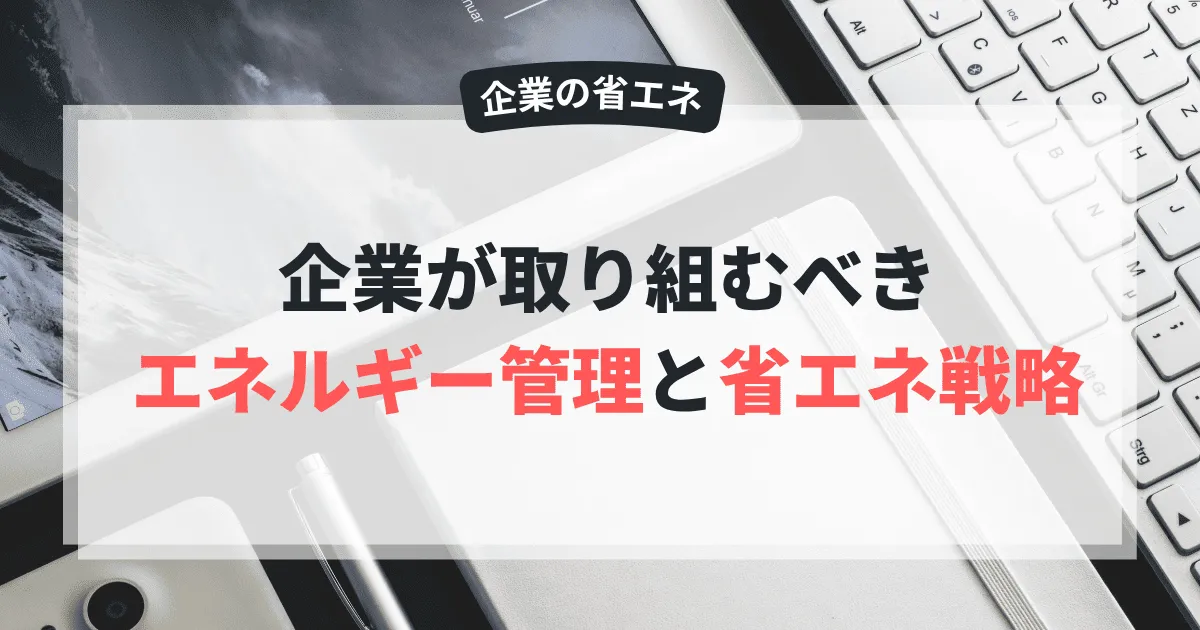
企業におけるエネルギーコストの増加や脱炭素への対応が求められる今、「エネルギー管理」は省エネを成功させるための欠かせない取り組みです。
しかし、多くの企業ではエネルギー使用量を正確に把握できておらず、効果的な省エネ施策が行えていないのが現状です。
本記事では、エネルギー管理が企業の省エネにどのような効果をもたらすのか、そして具体的にどのような施策を進めるべきなのかを、専門的な視点からわかりやすく解説します。エネルギーコストの削減と環境負荷の低減を実現したい担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
なぜ今、企業にエネルギー管理が求められるのか
エネルギー価格の高騰、脱炭素社会への移行、そして省エネ法の規制強化など、企業を取り巻く環境は急速に変化しています。とくに近年は電力料金が高止まりし、中小企業でも光熱費が経営を圧迫するケースが増えてきました。
こうした背景から「エネルギー管理」は、単なるコスト削減策ではなく、企業の経営戦略に直結するテーマへと進化しています。
また、ESG経営やカーボンニュートラルへの対応は取引先からも求められる時代。エネルギー管理の取り組みは、企業価値向上やステークホルダーからの信用獲得にもつながります。
そのため、今後は規模の大小に関わらず、エネルギーを“戦略的に管理する企業”と“放置する企業”で競争力に大きな差が生まれることが確実です。
エネルギー管理と省エネの関係性
エネルギー管理とは、企業が使用するエネルギーの量や効率を把握し、適切に運用・改善するための一連の仕組みを指します。
省エネは「消費エネルギーを減らすこと」を目的としますが、その土台となるのがエネルギー管理です。適切な管理ができていなければ、省エネ施策を行っても効果が出ない、または継続しないという問題が生じます。
逆に、管理体制を整えることでムダな消費が明確になり、効果的な省エネ手法が見えてきます。このようにエネルギー管理と省エネは密接に関わっており、企業が持続的にコスト削減と環境負荷低減を進めるためのセットとなっています。
エネルギー管理が省エネ効果を高める理由
エネルギー管理が省エネ効果を高める最大の理由は、企業全体のエネルギー使用状況を「見える化」し、ムダの所在を正確に把握できる点にあります。
多くの企業は、照明・空調・生産設備などのどこにどれだけのエネルギーが使われているかを把握できていません。見える化が進むことで、例えば「休日に空調が無駄に稼働している」「一部の生産ラインでピーク電力が突出している」といった本質的な課題が浮き彫りになります。
また、データを活用することで改善効果を数値として評価できるため、取り組みの優先順位付けや投資判断も合理的に進められます。さらに、現場担当者の意識改革にもつながり、省エネ活動が継続的に進む環境づくりが可能になります。このようにエネルギー管理は、単なる“削減のテクニック”ではなく、省エネを長期で成功させる基盤となるのです。
電力の見える化については、電力の見える化は必要?メリット・デメリット、成功事例を解説の記事で詳しく解説しています。
省エネを阻む企業の課題とよくある失敗例
企業が省エネを進める際に陥りがちな失敗として、「対症療法で終わってしまう」という点が挙げられます。
例えば、電気代が上がったからといってLED化や空調更新だけを実施しても、全体最適になっていなければ効果は限定的です。
また、担当者が変わると取り組みが途切れてしまう“属人化”も大きな課題です。エネルギー管理が仕組み化されていない企業では、担当者依存となり、データ管理が不十分なまま改善が継続しません。
さらに、削減効果を検証しないまま施策を実施するケースも多く、結果として「どの対策が効果的だったのか」が分からず投資判断が曖昧になります。こうした失敗を避けるには、エネルギー管理の基盤整備が不可欠であり、全社で取り組む体制づくりが重要です。
企業が実践すべきエネルギー管理の具体策
エネルギー使用量の見える化とデータ管理
見える化はエネルギー管理の第一歩であり、省エネのスタート地点です。
具体的には、電力・ガス・燃料などの使用量を、日単位・時間単位で把握できるようにすることが重要です。特に電力は“ピーク電力”の影響が大きく、契約電力の見直しやデマンドコントロールの判断材料になります。
また、生産設備や空調ごとに計測を行うことで、「どの設備がエネルギーコストを押し上げているのか」を特定できます。データを蓄積すれば、季節変動や設備の劣化なども可視化でき、計画的な改善が可能になります。
さらに、見える化したデータは改善策の効果検証にも活用でき、PDCAが回りやすい環境が整います。このデータドリブンな運用こそが、省エネを継続的に成功させる大きな鍵となります。
設備の最適運用と省エネ改善のポイント
省エネのためには、単に設備を更新するだけではなく「どう運用するか」が極めて重要です。空調設備では設定温度の適正化やフィルター清掃、運転スケジュールの見直しが効果的です。生産設備では負荷に応じたインバータ制御の導入や、アイドリング時間の削減などが挙げられます。
また、照明では人感センサーやゾーン別制御によって不要な点灯を防ぐことができます。「最新設備に入れ替えれば省エネになる」という思い込みは危険で、運用改善の方が費用対効果が高いことも多くあります。見える化データを活用しながら、設備の稼働状況を把握し、ムダな運転を抑えることが省エネ性向上の鍵です。
そして、これらの改善を継続するためには、担当者の意識改革と現場の協力体制が欠かせません。
エネルギー管理体制の構築と担当者育成
エネルギー管理を持続的に行うためには、明確な体制づくりと担当者の育成が必須です。
まず重要なのは、経営層が省エネの重要性を理解し、明確な方針を示すことです。現場任せにすると属人化し、取り組みが長続きしないため、組織としての責任範囲を明確に設定する必要があります。
また、エネルギー管理者や担当者には、法規制の理解だけでなく、データ分析や設備知識など幅広いスキルが求められます。定期的な研修や外部講習の受講も効果的です。さらに、全社的な協力を得るためには、社内での情報共有や成功事例の可視化が欠かせません。こうした体制が整うことで、省エネ活動が“仕組み”として根づき、長期的に高い効果を生み出します。
省エネ効果を最大化するための戦略
費用対効果を高める省エネ投資の考え方
省エネ投資で最も重要なのは費用対効果の最大化です。見た目の削減額だけに注目するのではなく、投資回収期間(ROI)を指標に判断することで無駄な投資を避けられます。
また、投資額の大きい設備更新に踏み切る前に、運用改善や制御機器の導入など、低コストで効果の高い施策を優先することがポイントです。さらに、設備の稼働データを基にシミュレーションを行うことで、導入後の効果を事前に予測できます。複数の施策を組み合わせたシナジー効果も考慮することで、総合的な省エネ効果を高められます。
エネルギー管理がしっかり行われていれば、これらの投資判断が格段に合理的になり、企業の経営効率向上にも大きく貢献します。
補助金・制度を活用した効果的な省エネ推進
省エネを進めるうえで、国や自治体の補助金を活用することは非常に効果的です。特に中小企業にとっては、設備更新やシステム導入の初期費用を大幅に抑えられるため、取り組みを加速させる大きな後押しになります。
代表的なものには「省エネ補助金」「中小企業等事業再構築補助金」「設備導入促進のための補助金」などがあり、年度ごとに要件や対象は変わりますが、省エネ設備や管理システムの導入で活用できるケースが多くあります。補助金申請にはエネルギー削減効果の数値化が求められるため、エネルギー管理によるデータ蓄積が大きく役立ちます。
また、補助金を活用することでより高度な省エネ設備の導入が可能となり、長期的な経営メリットを得やすくなります。
まとめ
エネルギー管理は、省エネを実現するだけでなく、企業の競争力を高める重要な経営戦略です。見える化・運用改善・体制構築・補助金活用を組み合わせることで、継続的なコスト削減と脱炭素への貢献が可能になります。
「エネルギー管理 省エネ」のキーワードを軸に、企業が今取り組むべき方向性を明確にし、持続可能な経営を実現しましょう。
エネトクは、これまで18,000社以上の企業様の省エネ・コスト削減の支援実績があります。電力の見える化と空調自動制御によりエネルギー管理と省エネが可能なエネルギーマネジメントシステム”EM CLOUD”を提供しており、コスト削減への専門的なアドバイスも可能です。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 【事例あり】物流倉庫で効果的な省エネ方法5選!
【事例あり】物流倉庫で効果的な省エネ方法5選! 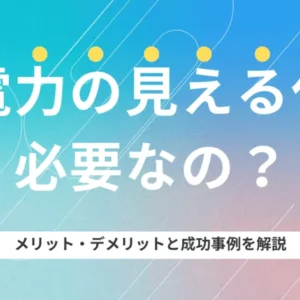 電力の見える化は必要?メリット・デメリット、成功事例を解説
電力の見える化は必要?メリット・デメリット、成功事例を解説 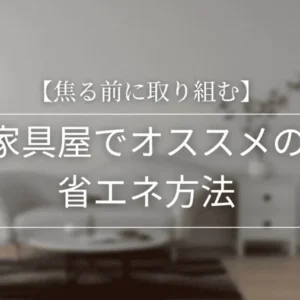 【焦る前に取り組む】家具屋でオススメの省エネ方法と成功事例を紹介
【焦る前に取り組む】家具屋でオススメの省エネ方法と成功事例を紹介 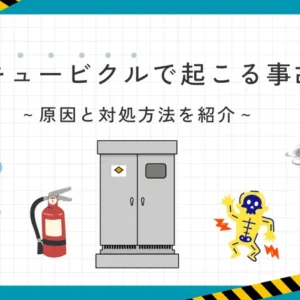 キュービクルで起こる事故~原因と対処方法を紹介~
キュービクルで起こる事故~原因と対処方法を紹介~ 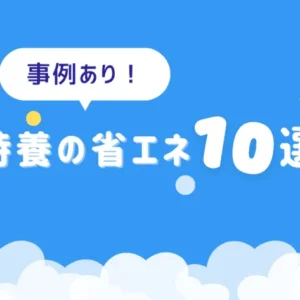 特養の経費削減に効く省エネ対策10選|現場でできる節電術
特養の経費削減に効く省エネ対策10選|現場でできる節電術