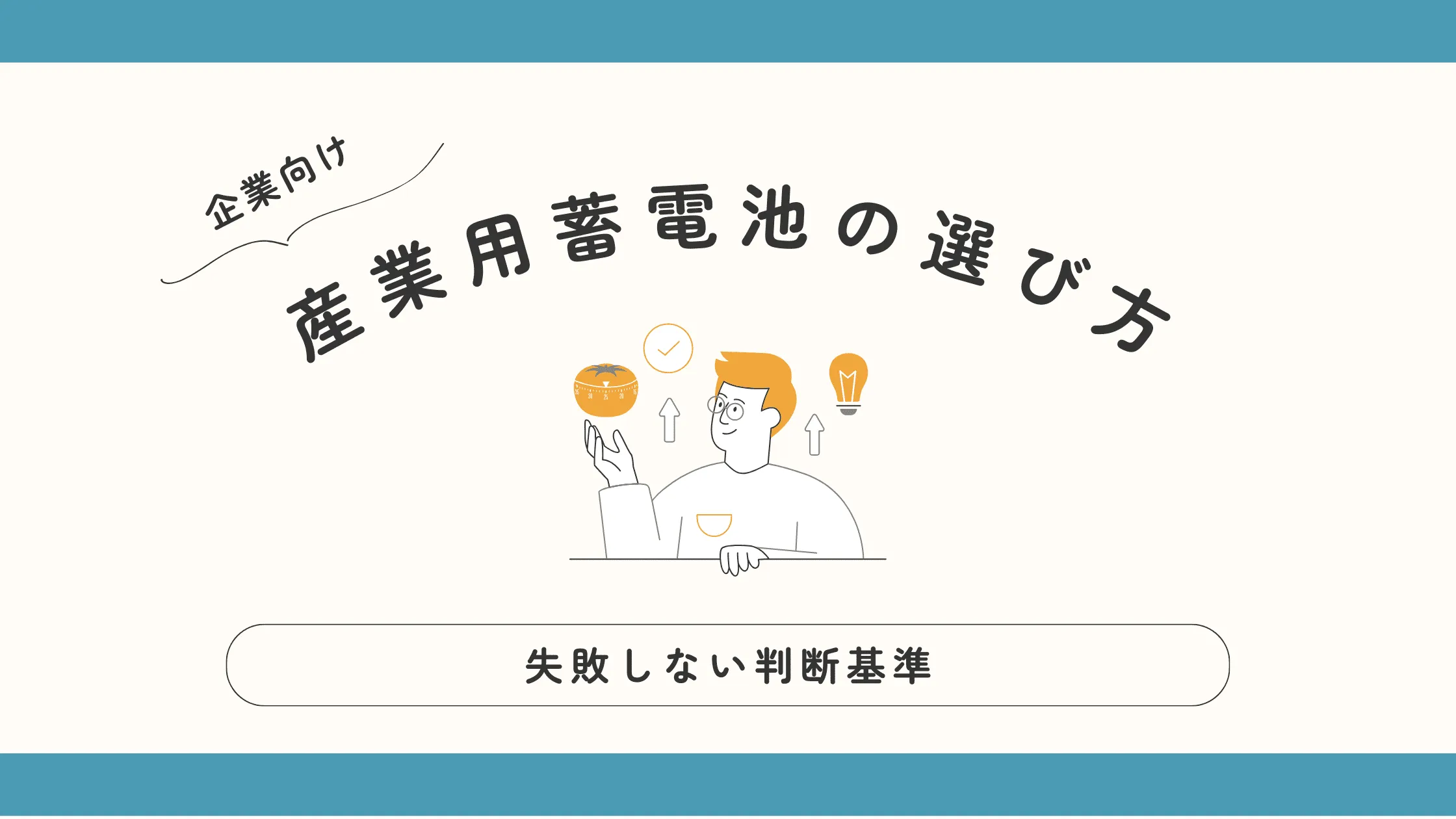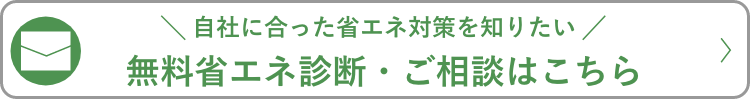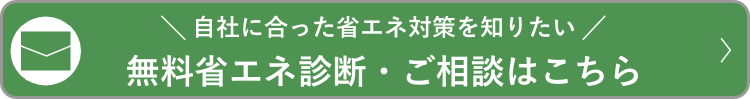投稿日:
【目から鱗】業務用エアコンの電気代はいくら?電気代シミュレーションと削減のコツ

業務用エアコンは、企業活動における電力消費の中でも特に大きな割合を占める設備の一つです。
業務用エアコンの月間の電気代は、「消費電力×台数×使用時間×電力量料金単価」で算出することができます。
夏季・冬季における稼働時間の増加は、月間の電気料金に大きなインパクトを与える要因となります。
とはいえ、「実際の電気代はいくらか」「削減余地がどの程度あるのか」が把握できていない企業も少なくありません。
本記事では、「業務用エアコン 電気代」の基本的な目安から、簡単なシミュレーション方法、電気代に影響する要因、そして中長期的な視点を含めた6つの節電対策までを体系的に解説します。
施設管理・エネルギーコストの最適化を目指す担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
業務用エアコンの電気代はどれくらい?
一般的な電気代の目安(月額・日額・時間あたり)
業務用エアコンの電気代は、機種や使用状況によって大きく異なりますが、一般的な目安を把握しておくことは重要です。
例えば、5馬力(約14kW)のエアコンを毎日10時間稼働させた場合、1時間あたりの電気代は約80〜100円程度とされており、1カ月では約24,000〜30,000円に達します(電力量単価:30円/kWhで計算)。日額では約800〜1,000円です。もちろん、これは連続稼働を前提とした場合であり、休業日やアイドルタイムがあればこれより下がります。
こうした平均値を知ることで、自社の電気代が高すぎるかどうかの判断材料になります。月額が10万円を超えるようなケースでは、何らかの無駄が潜んでいる可能性もあるため、早めの見直しが重要です。
業種別・施設規模別の電気代の違い
業務用エアコンの電気代は、業種や施設の規模によっても大きく変わります。
たとえば、飲食店では厨房機器による熱が加わるため冷房の負荷が高くなり、電気代が跳ね上がる傾向があります。
一方、オフィスでは人の出入りが少なく、設定温度を安定させやすいため比較的低コストです。
また、病院や介護施設のように24時間稼働が必要な業種では、稼働時間が長いため電気代の総額が非常に大きくなります。さらに、店舗の広さによって必要な馬力数が増えれば、それに比例して消費電力も上昇します。
こうした背景から、自社の業態に適したエアコンの使い方や契約内容を見直すことが、電気代削減の第一歩となるのです。
業務用エアコンの電気代を左右する3つの要素
使用時間と稼働日数
業務用エアコンの電気代に最も影響を与える要因の一つが「使用時間と稼働日数」です。
たとえば、同じエアコンを導入していても、1日8時間稼働する店舗と12時間稼働する施設とでは、月間の電気代が大きく異なります。さらに、週休2日の事業所と年中無休の店舗でも、累積の電気使用量に差が生まれます。
業務用エアコンは、基本的に稼働時間に比例して電気代がかかるため、長時間稼働する環境ではそれだけコスト負担が大きくなります。逆に言えば、稼働時間を見直すことで電気代を抑えることができるということです。
例えば、ピーク時以外の温度設定の見直しや、一時的に電源をオフにする工夫など、時間帯別の運用を最適化することで、稼働時間の削減につながります。まずは1週間の稼働ログを取り、無駄な運転時間がないかを洗い出すことから始めましょう。
エアコンの馬力(能力)と機種の違い
業務用エアコンには「馬力(HP)」という単位で冷暖房能力が示されており、この馬力数が大きくなるほど消費電力も上がります。たとえば、2馬力の小規模向けモデルと10馬力の大型モデルでは、1時間あたりの消費電力が数倍違います。
また、機種によっても電気代に差が出ることは意外と知られていません。インバーター制御が搭載されている機種であれば、出力を自動調整して必要な電力だけを使用するため、電気代を大幅に抑えることができます。
逆に、旧式のオンオフ制御エアコンでは常にフル稼働するため、無駄な電力消費が発生します。電気代が高いと感じたら、馬力が過剰ではないか、機種が古すぎないかも確認しましょう。最新モデルへの更新は初期費用こそかかりますが、長期的に見ると電気代の削減効果が非常に大きく、投資対効果の高い施策になります。
業務用エアコンの種類については、【丸わかり】業務用エアコンの種類はこれだけ見れば間違いなしの記事で詳しく解説しています。
設置環境とメンテナンスの状態
業務用エアコンの効率は、設置環境によっても大きく左右されます。たとえば、日当たりの強いガラス張りのオフィスや、断熱対策が不十分な建物では、エアコンに余計な負荷がかかり、冷暖房効率が悪くなります。
また、吹き出し口の前に什器や棚が置かれていると空気がうまく循環せず、設定温度を保つために余計な電力を消費することになります。さらに見落としがちなのが、エアコンのメンテナンス状況です。フィルターにホコリが詰まっていたり、熱交換器が汚れていたりすると、冷暖房効率が低下し、消費電力が増加します。少なくとも月に1度はフィルターを清掃し、年に1〜2回は専門業者による点検・洗浄を行うことで、性能を維持し電気代の無駄を防ぐことができます。
省エネ対策は機器の選定だけでなく、使用環境やメンテナンスの徹底にも目を向ける必要があります。
電気代を計算する方法
消費電力×台数×使用時間×稼働日数×電力量料金単価
業務用エアコンの月間の電気代は、「消費電力×台数×使用時間×電力量料金単価」で近似値を算出できます。
たとえば、消費電力12.5kWのエアコンを1日8時間、30日間使用し、電力量単価が30円/kWhであった場合、「5.0×8×30×30= 36,000円」となります。
ポイントは、「消費電力=冷房能力」ではなく、機種ごとに仕様書などで確認が必要なことです。
一般的に、能力(馬力)が高くなるほど消費電力も大きくなり、電気代に直結します。
また、電力量料金単価は契約プランや時間帯によっても変動するため、正確に算出したい場合は電力会社から提供される料金表を確認するのがベストです。概算であっても、この式を用いることで、現在の運用コストの見える化や節約の検討材料になります。
今すぐできる!電気代を抑える6つの節約術
1. 設定温度を最適化する
業務用エアコンの電気代を削減する最も基本的かつ効果的な方法が、設定温度の見直しです。冷房時は設定温度を1℃高く、暖房時は1℃低くするだけで、約10%前後の電力削減効果があるとされています。
たとえば、冷房の設定温度が24℃のまま固定されている職場では、25〜26℃への調整を検討してみましょう。特に、オフィスや店舗では人の体感温度にも差があるため、「室温でなく体感で判断する」ことが大切です。扇風機やサーキュレーターを併用することで、空気の流れが生まれ、体感温度を2〜3℃下げることが可能です。
また、夏場は西日対策としてブラインドや遮熱フィルムを活用すると、室温の上昇を防ぎ、エアコンへの負荷を軽減できます。誰でもすぐに取り組める方法だからこそ、社内での共有・徹底が電気代削減に直結します。
2. 定期的なフィルター清掃
業務用エアコンのフィルターにホコリや汚れがたまると、空気の流れが悪くなり、冷暖房効率が大きく低下します。結果として、必要以上に電力を消費し、電気代の増加を招きます。
メーカーの推奨では、使用頻度にもよりますが「2週間に1度のフィルター清掃」が理想とされています。特に飲食店や美容室など、空気中に油や髪の毛が舞う業種では、より頻繁な清掃が必要です。掃除は簡単で、フィルターを外して水洗いし、しっかり乾かして再装着するだけでOK。社員が自分で行えるレベルの作業でありながら、効果は絶大です。
さらに、フィルターだけでなく吹出口や熱交換器の清掃も重要です。年に1回程度は業者に依頼して内部洗浄を行うことで、機器の寿命延長にもつながります。メンテナンスコスト以上に節電効果が見込める、非常にコスパの良い対策です。
3. 人感センサー・タイマー活用
エアコンの稼働時間を効率化するうえで有効なのが、人感センサーやタイマー機能の活用です。
これらをうまく使えば、無人の時間帯や場所での無駄な運転を防ぐことができ、大幅な電気代削減が可能になります。
たとえば、会議室や倉庫など「常時人がいない場所」では、人感センサー付きのエアコンに変更するだけで、自動でオンオフが切り替わるため非常に便利です。さらに、始業前や終業後の運転時間をタイマーで調整することで、誰かが手動で操作しなくても適切な時間帯に自動制御できます。
また、近年の業務用エアコンには「省エネモード」や「AI自動制御機能」が搭載されているものもあり、利用状況に応じて消費電力を最適化してくれます。こうした機能を正しく理解し、社内での使い方をマニュアル化することが、継続的な省エネ運用に繋がります。
4. 最新型の省エネモデルへの買い替え
業務用エアコンの電気代が高くなる一因に「旧型機器の継続使用」があります。10年以上前のモデルと最新の省エネモデルを比較すると、年間の消費電力量が20〜40%も異なることがあります。これは、最新機種に搭載されているインバーター制御やAI運転などの高効率技術によるものです。古いエアコンは一定の出力で運転し続けるため電力の無駄が多く、室温に合わせて調整することができません。
買い替えは一時的に大きなコストがかかりますが、省エネ性能の高いモデルに変更すれば、月々の電気代が数千円〜数万円単位で削減されることも珍しくありません。
さらに、国や自治体の省エネ補助金制度を活用すれば、導入費用の一部を軽減できる可能性もあります。長期的視点で見れば、買い替えはコストではなく「投資」と捉えるべき施策です。
5. 電力契約プランの見直し
エアコンの使い方だけでなく、契約している電力会社やプランの見直しも、電気代削減に直結する重要なポイントです。特に高圧契約の事業所では、基本料金が「最大需要電力(デマンド)」によって決まるため、ピーク時のエアコン使用量が多いと、それだけで年間の基本料金が跳ね上がってしまいます。
また、契約プランによっては、昼間の電力単価が高く、夜間が安いといった時間帯別料金が設定されているケースもあります。電力の使用状況に応じて最適なプランを選ぶことで、同じ電力量でも支払う金額が変わるのです。
近年では、新電力会社との契約切替でコストを削減している企業も増加中。まずは過去1年分の電気使用量データと請求書を確認し、エネルギーコンサルティング企業や比較サイトを活用して最適プランを見つけるのが効果的です。
6. エネルギーマネジメントシステムの導入
工場や大規模施設など、電力使用量が多い事業所に特におすすめなのが「エネルギーマネジメントシステム」の導入です。これは、電力の使用ピークを監視し、自動でエアコンなどの機器を制御して、最大需要電力(デマンド)を抑制する装置です。
前述の通り、デマンド値が高くなると高圧契約における基本料金が上昇するため、この値をいかにコントロールするかが鍵になります。
エネルギーマネジメントシステムは、電力使用状況の見える化や、あらかじめ設定したルールに基づき、空調機器を段階的に制限したりすることで、無理のない省エネ運用を可能にします。人の手をかけずに自動でコントロールできるため、担当者の負担も軽減されます。
導入コストは高いですが、大きな事業所ほど投資回収期間が短く、コスト削減インパクトが大きいため、検討する価値は十分にあります。
エネルギーマネジメントシステムについては、エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?メリットや種類まで徹底解説の記事で詳しく解説しています。
まとめ
業務用エアコンの電気代は、企業の運営コストに直結する重要な要素です。
特に、夏場や冬場など冷暖房の使用が増える時期には、エアコンの電力消費が電気料金全体の半分以上を占めることもあります。本記事で解説したように、電気代は「使用時間」「馬力」「設置環境」「契約内容」など、さまざまな要因に影響されますが、適切な知識と対策を講じることで、大きな削減が可能です。
日々の運用の見直しに加え、フィルター清掃や設定温度の最適化といった小さな改善から始め、ゆくゆくは高効率モデルへの更新やデマンドコントローラー導入など、中長期的な施策も視野に入れていくとよいでしょう。また、電力契約や料金プランの見直しも見逃せません。電気代の「見える化」と「最適化」は、経営の健全化にもつながります。
エアコンは「つけっぱなし」ではなく、「戦略的に使う」時代です。今日からできる省エネ対策で、ムダなコストを削減し、利益率の向上につなげましょう。

 業務用エアコンEHPとGHPの違いとは?ランニングコストを抑えるために必要なポイント
業務用エアコンEHPとGHPの違いとは?ランニングコストを抑えるために必要なポイント  エアコンの冷媒ガスとは?種類やガス漏れした際の対処方法
エアコンの冷媒ガスとは?種類やガス漏れした際の対処方法 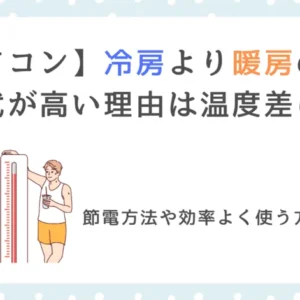 エアコン暖房の方が冷房より電気料金が高い!暖房と冷房の違いと節電のコツを解説【温度差にあり】
エアコン暖房の方が冷房より電気料金が高い!暖房と冷房の違いと節電のコツを解説【温度差にあり】 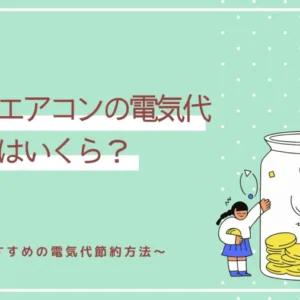 業務用エアコンの電気代はいくら?おすすめの電気代節約方法を紹介
業務用エアコンの電気代はいくら?おすすめの電気代節約方法を紹介  【初心者向け】エアコン掃除のやり方、掃除する部分は3つだけ!
【初心者向け】エアコン掃除のやり方、掃除する部分は3つだけ!