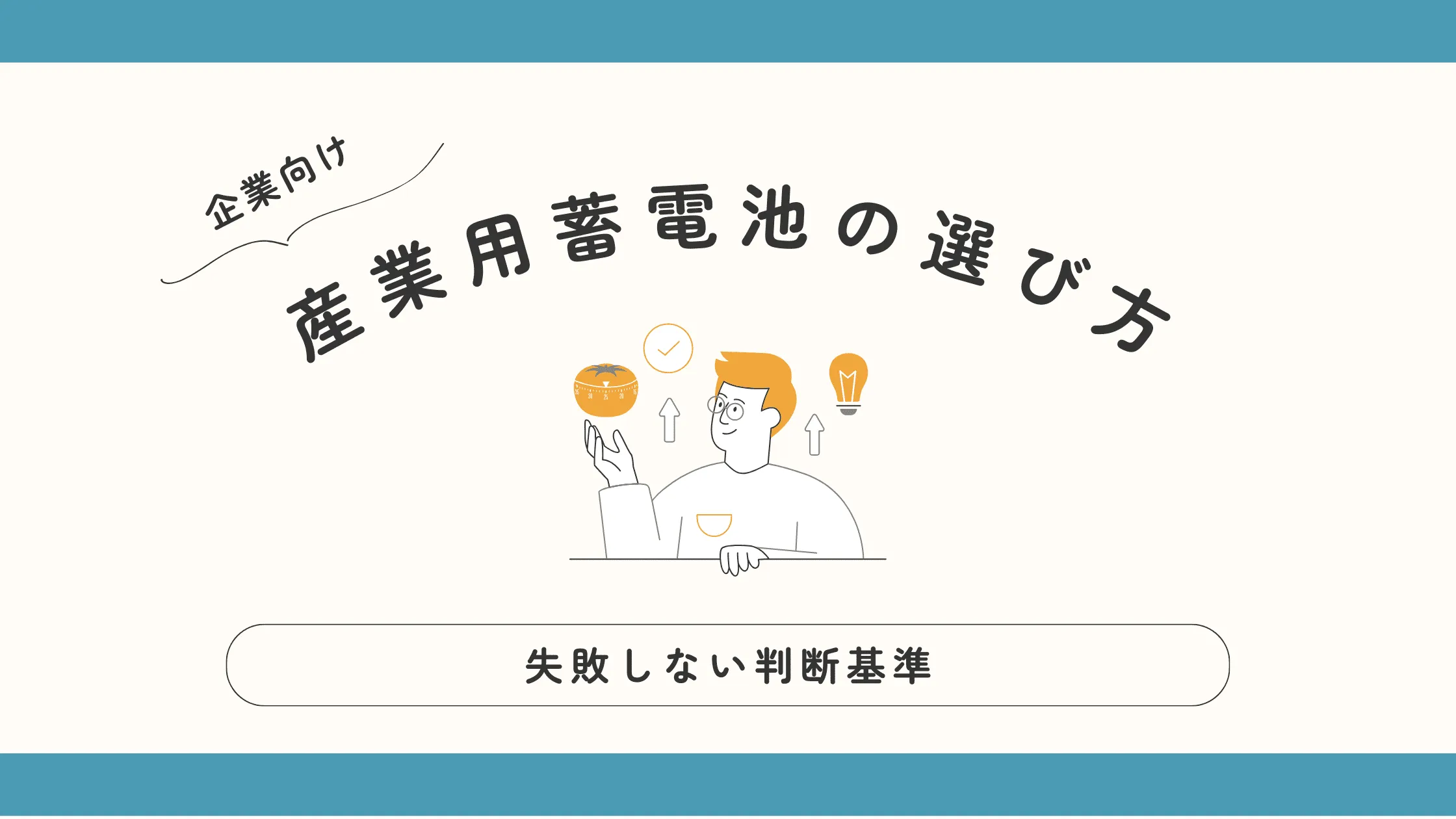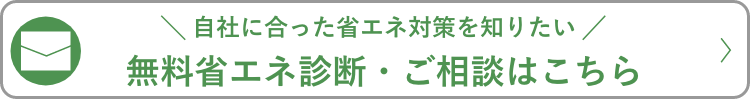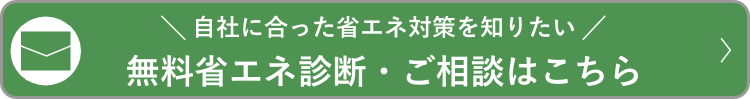投稿日:
【畜産従事者必見】酪農で省エネ対策が必要な理由とコスト削減につなげるコツを解説
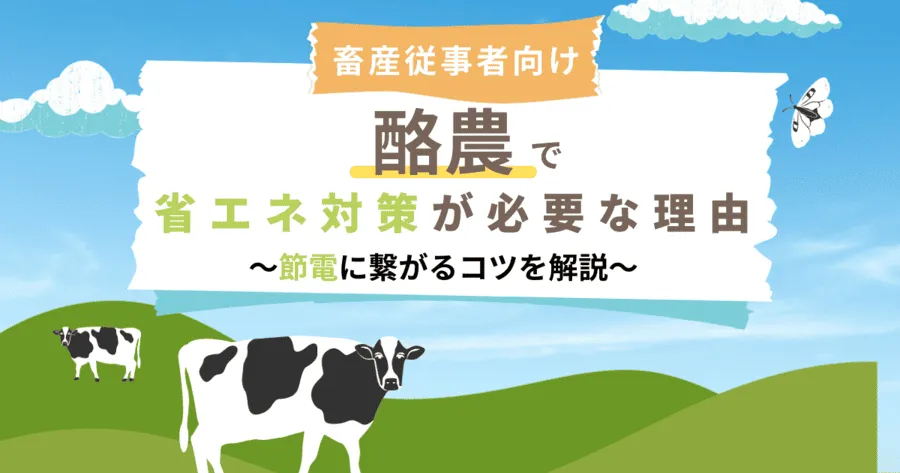
近年酪農においては、円安によるエネルギーコストの高騰が課題となっています。
そのため、これからの酪農においては省エネ化を進めていくことが必要です。
また、畜産業では動物由来の温室効果ガスの排出が世界的な問題となっており、環境負荷を減らすための省エネシステムが求められています。
しかし、「酪農で省エネ化はできるのかな?」「省エネ化のためには新しい設備の導入が必要なのだろうか?」というように酪農における省エネ化に不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では酪農における省エネ対策とエネルギーコストの削減につなげるコツを解説します。
ぜひ、酪農におけるエネルギーコストを抑えたい方は参考にしてみてください。
Contents
酪農におけるエネルギー使用量の現状
酪農経営は、電力依存度が高い産業です。
近年、作業の機械化が進み、ますますその傾向は強くなっています。
そこで、実際の酪農経営においてどのくらいのエネルギーが使用されているのか見ていきましょう。
電力使用量の大きい機器
効率よく省エネを行うためには、酪農で使われている機械の消費電力を正しく把握する必要があります。
そこで、酪農で使用される機械のうち、消費電力が大きいものから順に下記の表に記しました。
| 電気機器 | 消費電力割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 換気扇 | 41% | |
| バルククーラー | 20% | |
| 搾乳機器 | 15% | |
| 糞尿処理関係 | 15% | 調査対象に特殊な糞尿乾燥機導入例あり |
| 給餌関係 | 8% | |
| 照明 | 2% |
上記の表からわかるように、酪農で効果的に省エネを行うためには換気扇・バルククーラーに使われる電力を節電することが重要です。
そこで、上記の機械が酪農においてどのような役割を果たしているのか確認し、適切な省エネ対策を実践していきましょう。
換気扇が果たす役割
換気扇が果たす役割は「空気の入れ替え」と「暑熱対策」の2つです。
現在日本の酪農で行われている飼育牛舎の大部分が「繋ぎ飼い式牛舎」です。
この方法では、牛が区切られたスペースにスタンチョンやロープなどで繋がれているため、牛舎内にはアンモニアや二酸化炭素などの悪い空気がこもってしまいます。
そこで、それらの空気を入れ替えるために換気扇の稼働が必要です。
また、換気扇は夏になるとより長時間使用されます。
牛は一般的に暑さに弱い生き物です。
そのため、大型の扇風機を稼働させることで暑さ対策を行い、牛の体調管理に努めています。
バルククーラーが果たす役割
バルククーラーとは、搾乳した生乳を、乳牛工場へ向かう生乳者が来るまでの間保存するタンクのことです。
このとき、生乳を投入した最初の1時間以内に10℃、次の1時間までに4℃と温度が設定されています。
安全な牛乳を生産するためには欠かせない機械です。
酪農で省エネが必要な理由とは
酪農において省エネが必要な理由は下記の2点があります。
- 経営コストの削減
- 温室効果ガス排出の削減
それぞれ順に詳しく説明していきます。
経営コストの削減
近年の円安・世界情勢の悪化により、エネルギー費用、飼料代は高騰し続けています。
そのため、今までと同じように生産していたのでは、経営コストが増加し、利益が減少し続けることが現状の課題です。
実際、2023年3月に中央酪農会議が実施した「酪農経営に関する実態調査」によると、約85%の酪農家が赤字と回答しています。
また、赤字の要因の1つに燃料費・光熱費の上昇があげられています。
現在のエネルギー使用量を見直し省エネ化を図っていくことが、酪農経営に必要な経費コストの削減の大きな1歩となるでしょう。
温室効果ガス排出の削減
酪農を含む畜産業態の課題の1つとして、牛の生態に由来するメタンガスの排出があります。
メタンガスは地球温暖化に及ぼす影響が二酸化炭素に次いで大きいです。
牛などの反芻動物は消化の過程でメタンガスを排出するため、家畜からのメタンガスの排出は全世界の温室効果ガス排出量の6%を占めるとも言われています。
そのため、世界からの畜産業態に対する目線は厳しく、産業を縮小すべきという意見もあります。
だからこそ、畜産業態では省エネを行い、メタンガス以外の温室効果ガスの削減に取り組むことが必要です。
近年の技術革新によりメタンガスからエネルギーを取り出す事例もあるため、世界が抱える地球温暖化問題と、経営のためのコスト削減という2つの側面から、酪農家は省エネ化に取り組むことが重要です。
酪農における効果的な省エネ方法
酪農における具体的な省エネ方法について4つ紹介します。
- 太陽光パネルの設置で発電
- 牛糞を利用したバイオマス発電
- 舎内換気の改善
- 搾乳時間の短縮
太陽光パネルの設置で発電
発電を行い電力を増やすことで、電気代のコスト高騰に左右されにくい環境を作ることができます。
そのための手法の1つが太陽光発電です。
酪農においては、牛舎に設置する「屋根型太陽光パネル」が一般的です。
また、放牧地を持っている酪農家では、牛舎だけではなくさらに広大な土地を活用して太陽光発電を導入することができます。
さらに、畜産業界においては太陽光を農業生産と発電で共有して活用する「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」も普及中です。
牧草地に支柱などを立てて、その上部に設置した太陽光パネルを使って日照量を調整することで、酪農で使用する牧草の確保と発電の両立がおこなえます。
太陽光発電設備や定置用蓄電池のような電力エネルギーに関する設備は、国から補助金が出る場合もあるので、十分確認してから購入・申請するようにしましょう。
牛糞を利用したバイオマス発電
酪農家が省エネを進める理由の1つに「温室効果ガスの発生抑制」があります。
バイオマス発電とは、牛の糞尿に含まれるメタンを発酵させて生成したバイオガスを利用して行う発電方法です。
バイオマス発電により、牛の糞尿に含まれ大気中に放出される予定だったメタンが燃料になり、牛由来のメタン排出量削減に繋がります。
牛の糞尿は毎日排出されるものであり、その処理を行うことにもコストが必要です。
実際、糞尿処理にかかる電力割合は同率3位で処理方法を変えることで省エネ化になり、大きなコスト削減が見込めます。
さらにバイオマス発電に変更することで、糞尿処理機械の省エネ化だけではなく、電力を生み出すため、酪農で使用する他の機械への電力供給が可能です。
ただし、バイオマス発電を行うためには安定した糞尿の確保が必要で、小規模な酪農家単独で行うことは困難です。
そこで、同じ地域内の複数の酪農家による共同の発電処理システムを導入することをおすすめします。
舎内換気の改善
酪農における電力消費が大きい機械が換気扇です。
牛舎ににおいを発生させない工夫を行うことで、換気扇の稼働時間を短縮し省エネ化できます。
そのための有効な手段が「糞尿の早期分離と搬出・清掃」と「敷料の敷きこみ」です。
まず、牛舎内の臭気は堆積している糞尿の量に左右されます。
そのため、においの原因である糞尿の早期搬出が重要です。
尿の中に含まれる尿素に糞の中の微生物が反応することでアンモニアが発生し、臭気が強くなります。
そこで、糞と尿をできるだけ分離しながら搬出し、清掃を行うことが牛舎内の空気環境の維持には欠かせません。
そして、敷料は臭気対策の観点からも有効です。
臭気が敷料に吸着することで、空気中の臭気は低減します。
また、敷料は水分も吸収するため空気の乾燥が促進され、臭気が悪化しにくいです。
綺麗な牛舎の維持は、換気扇の省エネ化だけではなく、牛のストレス低減にも役立ちます。
さらに、清掃のタイミングを工夫することで、清掃にかかる時間や労力を減らせ、家畜と人間の両方に良い環境を生み出せます。
搾乳時間の短縮
搾乳は酪農作業の消費電力の中でも、大きな割合を占めます。
そこで、1回にかかる搾乳時間を短縮することで、真空ポンプの稼働時間を短くし省エネに繋げます。
「搾乳刺激のかけ方」と「ユニット装着のタイミング」に注意することで、搾りきりの悪さを解消し、効率のいい搾乳が可能です。
搾乳刺激に関しては、1乳頭につき4回絞るしっかりとした前絞りを行いましょう。
ユニット装着では乳が下りてきて乳頭が張るタイミングがベストなため、最初の搾乳刺激から60~90秒を意識して装着してみてください。
酪農におけるおすすめの省エネ設備3選
酪農におけるおすすめの省エネ設備を3つ紹介します。
- 空調システム
- ヒートシールド工法
- ミルクヒートポンプシステム
空調システム
多くの牛舎にはエアコンが設置されておらず、従来であれば窓を開けたり、換気扇・扇風機で空気の流れを良くしたりすることが多いです。しかし、近年酷暑が続いたため、牛舎にエアコンを導入する酪農家も増えています。
エアコンの導入により、牛が快適に過ごすことができ、乳量を大きく減らすことなく生産できます。さらに、エアコンには除湿機能もあり、乾燥した空気の送風が可能です。
温度だけではなく、湿度も下げることで、乳牛の特徴的な病気である「乳房炎」の罹患を予防することができます。
湿度が低い風を送風できるエアコンを利用することで、効率よく牛舎内を冷やして機械の稼働時間を短縮できるため、省エネ化に繋がります。
また、従来の換気扇・扇風機を利用するときにも省エネ化は可能です。
換気扇・扇風機の利用時は効率よく空気の入れ替えをすることがポイントです。
空気の通り道に障害物がないか、牛の体に風が当たるような風向きになっているか、設置場所に注意しましょう。
ヒートシールド工法
遮熱材を用いたヒートシールド工法とは冷気・暖気の熱が持つエネルギーの移動を抑えるための工法です。
太陽からの輻射熱を97%反射するため夏は涼しく、また冬は外の冷気と中の暖気をそれぞれ反射するため暖かい環境を作り出せます。
そのため、気温による家畜の環境ストレスを減少し、光熱費の省エネ化を図れます。
新しく建築することが難しい場合は、すだれ・寒冷紗を利用することで、牛舎に入る直射日光を防ぎましょう。
それにより、牛舎内の急激な温度上昇を抑制でき、空調システムの負荷を軽減し省エネで最大限の効果を期待できます。
ミルクヒートポンプシステム
ミルクヒートポンプシステムは、搾乳時の廃熱を機器洗浄のためのお湯を作る熱として利用するシステムです。
通常、搾ったばかりの温かい牛乳をバルククーラーで冷却する際には、熱が放出されます。
その熱をヒートポンプで回収しお湯を作る熱とすることで、ボイラーで使う灯油や牛乳予冷のために捨てられていた水道水の削減に繋げ、省エネ化に取り組めます。
このシステムは、バルククーラーで使われる電力を利用することができ、酪農における消費電力の有効活用が可能です。
また、急速に冷却されるため、菌の増殖を防ぎ、牛乳の品質の向上にも繋がります。
ヒートポンプシステム稼働による増加電力は、予冷によるバルククーラーの削減電力と相殺されるため、システム導入により電力が増加することはありません。
酪農の省エネ成功事例
酪農において、実際にどのようなシステムを取り入れて省エネを成功させているか具体的に紹介します。
北海道新エネルギー事業組合
北海道新エネルギー事業組合では、電気会社・設備会社が運営している組織です。現在7戸の酪農経営で稼働しています。
100頭規模の酪農経営に導入した場合、年間約60万円の節減に繋がります。
導入額は約400万円のため、この投資額は6~7年で回収が可能です。
そのため、7年以上の使用で省エネだけではなく、コスト削減にもつながります。
有限会社山川牧場自然牛乳
有限会社山川牧場自然牛乳では、日本テクノのSMART CLOCKとSMARTMETER ERIAを導入しました。
これにより、電気使用量のピーク時間を可視化し、作業時間を変えることで電気代のデマンド値の減少に成功です。
今稼働すべき作業と、そうではない作業を区別して作業を行うことで、電気の使用を抑え省エネ化の実現に繋げています。
その結果、契約電力は約20%カットし、使用電力も約3%削減しました。
まとめ
酪農家を取り巻く環境はどんどん厳しくなっており、コスト削減といわれても難しいイメージがあるかもしれません。
しかし、自身が経営する農場のどこにどのくらいの電力を利用しているのか正確に把握し、改善や必要に応じて投資することで、実現できる省エネが必ずあります。
省エネ化は経営コストの削減だけではなく、地球環境にも寄り添い、共に発展していくために必要な行動です。
特に、酪農においては現状を見直すことが省エネだけではなく、家畜の環境向上にも繋がり、生産性も高まるでしょう。
今回は、今すぐできる作業から長期的な未来を見据えて必要なシステム作りまで紹介させていただきました。
酪農業がこれからも発展していくための参考にしていただければ幸いです。
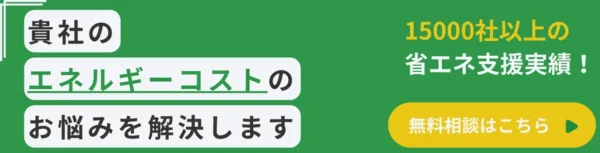
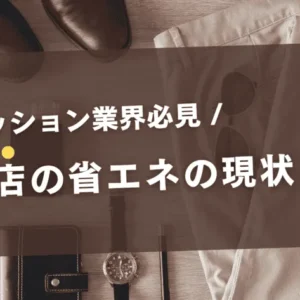 衣料品店における省エネの現状は?効果的な対策も含めて解説!
衣料品店における省エネの現状は?効果的な対策も含めて解説! 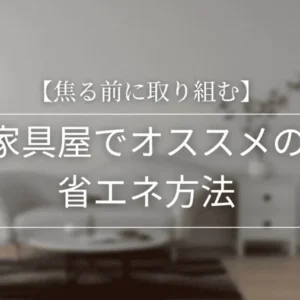 【焦る前に取り組む】家具屋でオススメの省エネ方法と成功事例を紹介
【焦る前に取り組む】家具屋でオススメの省エネ方法と成功事例を紹介 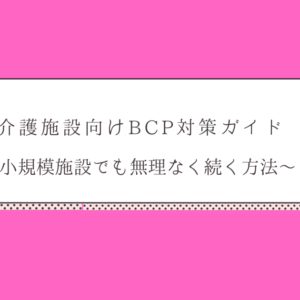 介護施設向けBCP対策ガイド|小規模施設でも無理なく続く方法
介護施設向けBCP対策ガイド|小規模施設でも無理なく続く方法  【今がチャンス】助成金でお得に感染症対策&省エネ!
【今がチャンス】助成金でお得に感染症対策&省エネ! 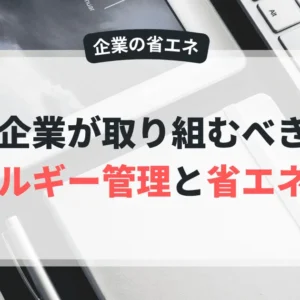 企業が取り組むべきエネルギー管理と省エネ戦略
企業が取り組むべきエネルギー管理と省エネ戦略